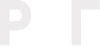
2021.10.11
レガシーの残し方としての「1%・フォー・アート」
#SHORT COLUMN
社会における芸術家の居場所を確保する「1%・フォー・アート」
このパブリックアートに関しては、日本では法制化されていませんが、戦後、世界中でこのような法令が制定されました。フランスで1950年に法令化された「1%装飾」制作や、アメリカの「パーセント・フォー・アート」は、公共建築を建設する際に、総予算の一部を美術作品の設置・購入に振り当てることを義務付けています(*1)。中国や台湾、韓国にも同様の取り組みがあり、日本でもこの法令を求める声があがっています。
とはいえ、この「1%・フォー・アート」は、やや強引な法律という気もしてきます。公共建築を作るときには「必ず」その1%をアートにする、となると、その建築物の規模にもよりますが、ある意味では大きな金額を美術作品に割くことになります。とはいえ、パブリックアートというものは、もちろん公共の空間にあるもの。例えば、毎日渋谷の駅を乗り換えで使うひとにとって、岡本太郎のあの絵は、「鑑賞」されるものではなく、目の端にすら止まらないようなものなのではないでしょうか。するとこれは、誰も見ないかもしれない作品にお金を割くということにもなりかねないのです。
それでも、こうしたパブリックアートが推進されているのはなぜなのでしょうか。
そもそも、この法令は、戦後の不況のなかで仕事をなくした芸術家に仕事を与えるためにはじまったといわれています。他の仕事をなくした労働者に向けた施策と同様に雇用の機会を創出するものでした。
1963年、アメリカの第35代大統領のジョン・F・ケネディは、パブリックアートを、単に鑑賞して楽しむだけのものと言うよりは、「アメリカの芸術的水準を確実に向上させるもの」と位置づけ、以下のように発言しています。
法律や法令の変化によってゆるやかに人々の意識が変わっていく
結局のところ、無観客で終わったオリンピックは、当初期待していた経済効果をもたらすこともなかったわけですし、重い負のレガシーがこれからのわたしたちを苦しめる可能性すら垣間見えてきています。
レガシーには、パブリック・アートやスケートボード・パークのような有形のものに加えて、無形のものもあります。無形のレガシーとして、オリンピックで掲げられた「多様性と調和」という理念がありますが、現状の日本でこの考え方が根付くのは、まだまだ時間がかかりそう。そんななかで、パブリック・アートの設置を推進する法令は、有形の文化財によって、無形のレガシーをのこすものとなりえます。「多様性と調和」というスローガンも、4年に一度ではなく、芸術においては常に示されてきた課題と言えるでしょう。
このように、社会が芸術家の居場所を確保する、その方法としてパブリック・アートを推進する「1%・フォー・アート」などの法令があり、欧米はもちろん、近隣アジア諸国と比較しても日本の文化芸術への取り組みの遅れは、この法令への態度にも現れています。米国で同性婚への理解が、同性婚の合法化によって「反対派」だった人々にも浸透していったように、法律や法令の変化によってゆるやかに人々の意識が変わっていくことがあるのです。有形のレガシーとしてのパブリック・アートが存在の一方で、実は、理解の第一歩としての「法令」が効果的な無形のレガシーなのかもしれません。
1 工藤安代『パブリックアート政策』(勁草書房、2008)
2 Camelot’s Legacy to Public Art: Aesthetic Ideology in the New Frontier Author(s): John Wetenhall Source: Art Journal , Winter, 1989, Vol. 48, No. 4, Critical Issues in Public Art (Winter, 1989), pp. 303-308